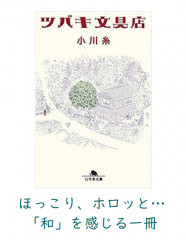言の葉通信
ちょっとした時間にでも…
少しずつ問い合せ電話をいただくようになり、少しずつ国語を学びたいと入塾する生徒も決まってきて、新しいお仕事(人生)が動き出したなぁと実感する日々。新しい人との繋がりにも喜びを感じる。
フリースペースとして勉強や読書ができる場所も併設しているが、意外に、大学生や社会人の方に利用していただいている。意外に…というのは、もともと高校生に多く利用してもらえたらと考えていたからである。
いわゆる「起業」を考えるようになったのは、12年ほど前に遡る。会議などで出かけた先々で、高校生になった教え子たちが勉強している姿を見かけるようになったことがきっかけだった。図書館で、とかちプラザで、駅構内で、スーパーの一角で… 下校後、家に帰る前に勉強できる場所を求めていることを知り、自習室のような場所があればいいのにと思ったのが最初だった。そんな場所を作ってあげられたらと。
同時期、常に5~7学級という多人数に国語の授業をする中で、限界を覚え始めてもいた。もっと一人一人に丁寧に教えたいと思うようになっていた。
そうして第2の仕事について真剣に考え始め、計画し、準備を進め、開業に至る。
ずっと中学生ばかりを見てきた教員生活だったからか、そこを巣立った高校生が気になってしまう。バスの待ち時間、親の迎えの待ち時間、ちょっと勉強して帰ろうかなと思ったときに「言の葉の森」に立ち寄ってもらえたら、この上なく嬉しい。
読書で「涙活」!?
本を読んで涙腺が緩むことは以前からあった。ドラマや映画を観ていても然り。それにしても、最近、特に涙もろくなったなぁと感じる。
たとえば朝ドラ「おかえりモネ」で…… ガンを患う写真家の田中さんが、送られてきた孫の写真を眺め、誰が撮ったんだか下手くそな写真だとけなし、「俺が最高の一枚を撮ってやるってんだ、もう…」と言っている姿に涙がポロッ…。こんな調子だから、いかにも涙を誘うような場面があったなら、気づけば嗚咽。我ながら、おいっ、ここでかよ!!と突っ込みたくなる。
現在私が読んでいる本は、乃南アサ『六月の雪』。日本の植民地であった時代の台湾で過ごしていた祖母の足跡を辿る孫娘の旅を描いているのだが、当然台湾の歴史等も描かれていて、これがまた涙を誘うのだ。
私が本を読むのはいつも寝る前、ベッドに入ったあと。『六月の雪』を読み始めてからは、ダメだ、これ以上寝る前に泣いてられない…と思って本を閉じることが多い。そうして朝まで爆睡…。
ところが、これがとても良いらしいのだ。寝る前に泣くと、自律神経が整い、リラックスして快眠できるとか。これを「涙活(るいかつ)」と言い、心のデトックス効果が抜群なのだそうだ。
確かに、思いっきり泣いた後はスッキリする。
寝付けない夜は、泣ける本を読むことにしよう!
ツバキ文具店
鎌倉で小さな文具店を営むかたわら、手紙の代書を請け負う鳩子。今日も風変わりな依頼が舞い込みます。友人への絶縁状、借金のお断り、天国からの手紙……。身近だからこそ伝えられない依頼者の心に寄り添ううち、仲違いしたまま逝ってしまった祖母への想いに気づいていく。大切な人への想い、「ツバキ文具店」があなたに代わってお届けします。
メールやSNSといった電子ツールで気軽に連絡を取ることができる今の時代。便利だけれど何か物足りない。
「代書屋」に舞い込んださまざまな代筆依頼を請け負う鳩子の仕事の丁寧さには、まさに「和」の心を感じる。その人に適した手紙を仕上げるのに、万年筆で書くのかボールペンで書くのか、その筆の太さ、インクの色、便箋の紙質、封筒の色合い、切手のデザイン、書体… 電子ツールではここまでできない。その手紙がたとえ絶縁状であっても、間違いなく「心」が伝わる。
代書の描写の丁寧さだけでなく、鳩子の暮らしぶりも丁寧で… 鎌倉の雰囲気も心地よい。近所の方々との交流も温かい。人々の心が通った生活。私もこんな丁寧な暮らしがしたいと思った。
メールではなくて、大切な人に心を込めて手紙を書きたくなる、そんな作品です。
中学生に身につけてほしい「国語力」
中学生には、常に高校入試を意識しながら進めざるを得ないでしょう。ただし、ゴールは高校合格に留まらず、将来正しく日本語を使える人であってほしいと考えます。つまり、高校入試はゴールではなく、正しい日本語を使う人になるための通過点です。「国語」というのは幅広く奥深く、教員生活を30年過ごした私でさえ、制することができません。
ですから、国語科でのできる限りの知識や語彙、読解力を身につけながら、入試に向けた演習を取り入れていきます。
学力テストの出題範囲表を初めて見た中学一年生は、国語の出題範囲を見ると必ず戸惑います。「これ、教科書のどこですか?」と聞いてきます。「教科書の文章は出てこない」と伝えた途端、もう何を勉強したらよいのやら…と頭の中が真っ白になります。どんな文章題が出題されても、日頃の授業での積み重ねてきた知識や技能を使えばよいのですが、それが実感できていないから戸惑うのでしょう。そして語彙知識の広さによって左右されるというのも、学力テストや入試の手強さかもしれません。
また、国語での、とりわけ読解問題は、他教科と決定的な違いがあります。
それは、「国語だけが、問題用紙に答えが書いてある」ということです。
ですから、国語の得意な子や日常的に読書量が多い子にしてみれば「文章を読んで、書いてあることを答えるだけ」なので簡単に解いていきます。文法事項を除けば英語や数学のようなはっきりとした新出単元があるわけでもないので、「習ってないから分からない」ということがありません。したがってほとんど勉強する必要がなく、いわゆる「ノー勉」で高得点が取れてしまいます。ただし、答えはわかっても、答え方が違っていれば点数にならないというところが国語の難点でもあります。
国語は幅広く奥深い。どこまでも広く、どこまでも深い教科です。少しずつ語彙を増やし、的確に文章を読み取る力を身につけていくことが必要です。
「言の葉の森」では、読書を通じて語彙力・読解力を高めながら、その子が苦手とするところを重点的に演習を繰り返し、問題用紙に書いてある答えの見つけ方と答え方を身につけながら、高校入試対策にも力を入れていきます。
小学高学年に身につけてほしい「国語力」
高学年になると、中学校入学を意識し始める時期。「中一ギャップ」と言われるほど、中学校に入学した途端、小学校との学習の進め方の違いに子どもは戸惑います。そのギャップを少しでも解消するためにも、国語科では「基本的な日本語の使い方」をしっかりマスターしておきたいところです。
たとえば、文章を書くときには漢字と仮名を適切に使い分ける、送り仮名や仮名遣いに注意する、文字を正しく書くことです。さらに、高学年になると、文章を科学的思考で読むことも必要になってきます。
国語でいう「科学的思考」とは、何かを語るときに理由や根拠が必要になったり、「もし~ならば」というような決まった言い回しがあったり、図やグラフと文章を読み比べたり……。よく国語は答えがひとつではない、曖昧だと思われがちですが、それは間違いです。国語にもはっきりと答えを導き出せるし、しっかり文章を読み取れば答えを見つけることができます。文章を書くときにも文章の組み立て方を知っていれば、わりと簡単に記述できます。
中学生になると勉強が格段と難しく感じるのは、これまでは広く浅く、多くを認められながら答えられていたのが、「テストではこう答えるんだ!」みたいな、急に答えの範囲が狭まってしまう気がするからかもしれません。
小学高学年には「国語科の中一ギャップ」を感じることが軽減されるよう、文章を科学的な目で見ながら、読解力を深めることを目指します。